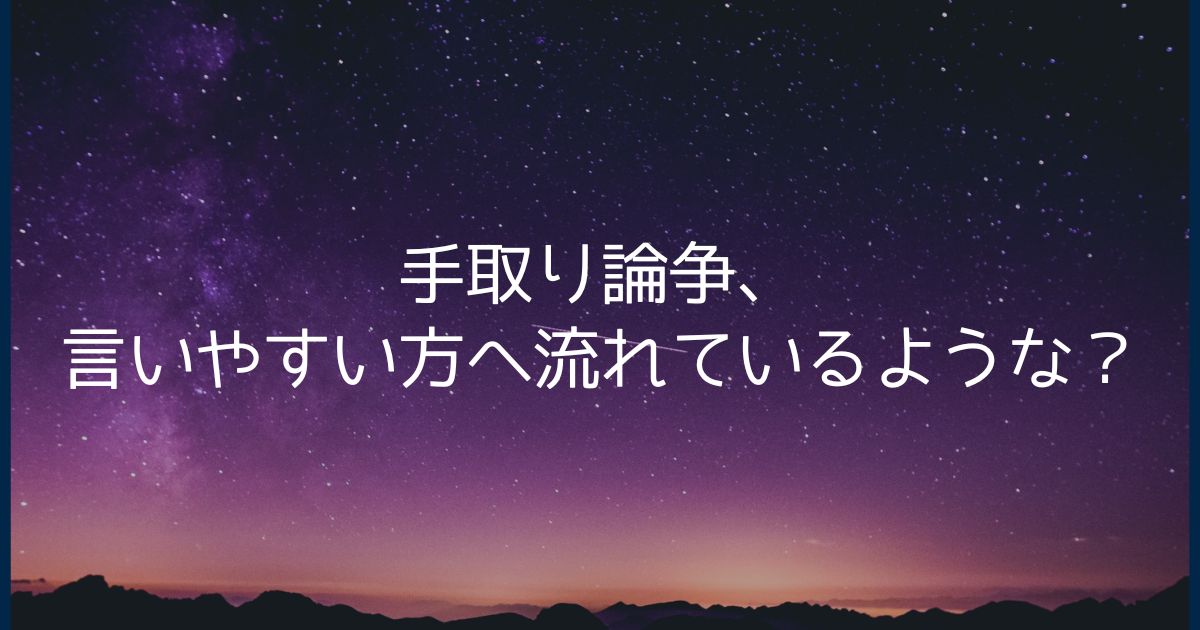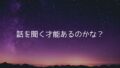こんばんは。
今日のテーマは「手取り」です。
前回の衆院選から急に「手取り増やせ」という主張が増えました。
まあ確かに、税金や特に社会保険料は高いですから、それを減らしてほしいという気持ちは理解できます。
ただ、問題はそれを進めると「小さな政府」が強まっていく点にあります。
「小さな政府」とは国家による支出を最低限にする代わりに税金も少ない体制です。
税金はともかくとして、社会保険料を減らすということは、社会保障が弱くなるということです。
日本では歴史学者の安丸良夫が指摘した「通俗道徳」が存在し、「自己責任論」が強まりやすい風土があります。すなわち、「働かざるもの食うべからず」「貧困の責任は貧困者本人にある」「そういった人は劣等処遇(一段低い扱い)せよ」といった雰囲気です。
社会保障はこれとは真逆で、「全ての人が平等に健康で文化的な生活が送れるようにする」というような思想を背景に持っています。(制度として不十分な面も多々ありますが)
よって、社会保障敵視論のようなものもよく見られます。「高齢者に金を回すな」的なやつですね。
しかし、ここで思うのは、そもそもなぜ「生活が苦しいのか」ということです。庶民同士で内戦をしている場合なんでしょうか。
生活が苦しい理由はいくつかの要素に分解できるのでしょうが、例えば以下の要素をあげることができます。
- 物価高騰(原因:円安)
- 消費税増税による物価高騰
- 社会保険料の増加
- 賃金の停滞
円安による物価高騰は要因が複雑に絡み合っているため、すぐに対処するのが難しいです。
真ん中2つは今、盛り上がっている話。(消費税は若干置いていかれている気がしますが)
最後の賃金の停滞は実は一番重要なのに、あまり語られていないポイントではないかと思います。
賃金の額面は増えている傾向にありますが、それが物価の上昇になかなか追い付かないという状態が長年続いてきました(直近やっと追い付きましたが、続くかは不明)。
また、労働分配率と呼ばれる会社の利益などを賃金に回す割合が日本は長年低下傾向にあり、世界的にも高くありません。
つまり、特に大企業において「もっと賃金に回せるのに、それを回さない」という状況があるわけです。
では、なぜそうなるのか。一番は日本の労働運動が非常に弱いためです。ヨーロッパと異なり、「会社単位の労働組合」での活動が基本なのに加え、労働組合なんて存在しないという会社も少なくありません。
よって、「賃金を上げろ」という声がそもそもとても小さいのです。国から賃金もっと上げてよ~なんてことを言ってもらっている始末です。
実は生活を楽にする最大の方法は「賃金を上げる」ことです。なぜか。社会保障を弱くすることと引き換えに減税路線に進んだ場合、社会保障が弱い分、結局は自費負担が増大していくからです。そうなった場合、結局「貯金しとかなきゃ」となるので、消費にも回りづらくなるでしょう。
となると、結局短期的には良くても、長い目で見ると「良かったのか?」となる可能性が高いです。
なので、やっぱり「賃金を上げる」ことが重要になります。
でも、会社にたてつくのって怖いじゃないですか。権威主義と呼ばれる「上の立場の人にはこびへつらい、下の人に威張る」という傾向を持つ人は少なくないでしょう。
だから、「賃金を上げろ!ストライキするぞ!」みたいな勇気がないわけです。私も無いけど(と言って、私はいわゆるサラリーマンではない)。
でも、減税の場合、短期的に困るのは社会的弱者ですし、「通俗道徳」「自己責任論」から社会的弱者に「劣等処遇」をするのは抵抗が無いんですよ。
よって、一番言いやすくて、お手軽な減税論に流れているのではないかと私は考えています。
よくよく考えて減税ではなくて、かなり単純に見えてるんですよね。
しかし、社会というのはそう単純ではないから、そんな「ノリ」みたいな感じで大丈夫か?という心配があります。
まあ、私自身もある程度の減税や社会保険料の減免(所得累進化)、給付の拡大など制度変更は必要だと思っていますが、もっとトータルで考えないといけないんじゃないかと思いますねえ。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
また、読みに来てくださいね。