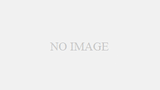私たちの社会はいつまでたっても不平等である。それはなぜだろうか?
まず一つ、意外なことがある。
実は私たちは平等が好きである。
様々な調査があるが、人間は基本的に平等を好むことはほぼ間違いない。
最近の神戸大学の研究では、この平等というのは「結果平等」であることも示されている。
(https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/2018_02_21_01/)
つまり、公平であることを好むのだ。
非力な子どもも力持ちの大人も同じものを運べというのは「平等」ではあるが、「公平」ではない。
私たちはこれを「不公平」ないし「不公正」だと感じ、嫌悪する。
たいていの人はこれに共感するはずだ。
しかし、実際の社会では不平等、不公平、不公正がまかり通っている。
これはなぜか。
実は平等を好むという研究の一方で、不平等を好むという反対の結果を示す研究もある。
基本的な傾向として、スケールが大きくなると不平等を容認するようになる。
(人は平等を好むが、不平等も好きだという研究)
これは人間の平等を好む心理は「近しい人」との間での「共感」によっているからかもしれない。
つまり、信頼関係があったり、自分の評判を落としたくないという相手との関係では平等を好むということである。
したがって、逆にどう思われても構わない、あるいはそういうことが想定されない相手を考えると不平等を容認するのではないだろうか。共感性、利他性よりも利己性が強く出てくるのではないか。
今後はこのあたりを調べたい。
もしそうなのであれば、私たちの社会はあまりに規模が大きすぎて、機能不全に陥っている可能性があると言えるかもしれない。例えば、自治体でも私の住んでいるところは人口25万都市であるが、人口が多すぎて、意思決定が機能不全に陥っていると感じる。同じ自治体でも自分の住んでいるところ以外の地域への関心を保つことは、容易ではない。
小規模分散型ネットワーク社会とでもいえる方向へ舵を切るべきではないかと個人的には考えている。