こんばんは。
今日のテーマは「贈り物」です。
普通、贈り物(プレゼント)って良いこととしてとらえられていますよね。
しかし、別の角度から見ると「贈り物」には「もらった人へ義務を生じさせる効果」があります。これは一種の暴力になり得ます。
レヴィストロースという有名な研究者がいるのですが、彼などが分析したのは「人は贈り物をすることで共同体を維持する」ということです。というのは、人は贈り物をしてもらうと「お返し」をしないといけないと感じるからです。これを「互酬性」(ごしゅうせい)と呼びます。
贈り物を交換することで人とのつながりを維持する。あるいは、もらった人が別の誰かへ贈り物をすることで、その共同体の中で富を回し、バランスを維持するのです。
しかし、このバランスが崩れると色々と困ったことが起きてきます。
例えば、AさんとBさんがいて、Aさんが目上だとしましょう。AさんはBさんにある日の食事をおごります。これは贈り物の一種ですね。しかし、たいていの場合BさんはAさんにおごり返すということはありません。これは目上の人が目下の人の世話をするという文化があるからです。
なので、BさんはAさんはその場でお礼を言うだけで終わります。
翌日、AさんとBさんが会った時、Bさんが昨日のことに触れなかったとします。Aさんはそれを不満に思いました。
こういうケースってたまに見聞きしますよね。
ここではAさんが想定した分の「お返し」がBさんからされなかったわけです。
ここでAさんがBさんに「こういうときはお礼を言うもんだ」みたいなことを言ったとすると、AさんはBさんに「お返しの強要」をしていると言えます。これは一種の暴力と見ることもできますよね。
同時にこれによって、AさんとBさんの間には「貸し借り」が生まれ、もとの関係以上に上下関係が生まれます。
返せないような贈り物を相手に贈り、貸しを作ることで、相手より優位に立つという効果が贈り物にはあるのです。
こう考えていくと、贈り物をもらうというのは良いことばかりでもないということになります。
なぜなら、常に「借りをつくって、下の身分へ転落するリスク」を背負うからです。
たまに障がいを抱えている方が「いつもお礼ばかり言うのはつらい」という趣旨のことを発信されることがありますが、これはこのリスクを常に感じるからではないでしょうか。
贈り物をするときは、それ自体が相手の負担にならないか気を付ける必要がありそうです。
また、いつももらう立場にある人は、別のところであげる立場になることで、少し気が楽になるかもしれません。そのときは、すぐに返せるような気楽なものが良いかもしれません。あるいは寄付のような見返りを求めないものでもいいかもです。
「贈り物は良いに決まっている!」と思い込んでいると、誰かに重荷を背負わせてしまうかもしれませんよ。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
また、読みに来てくださいね。
<参考>
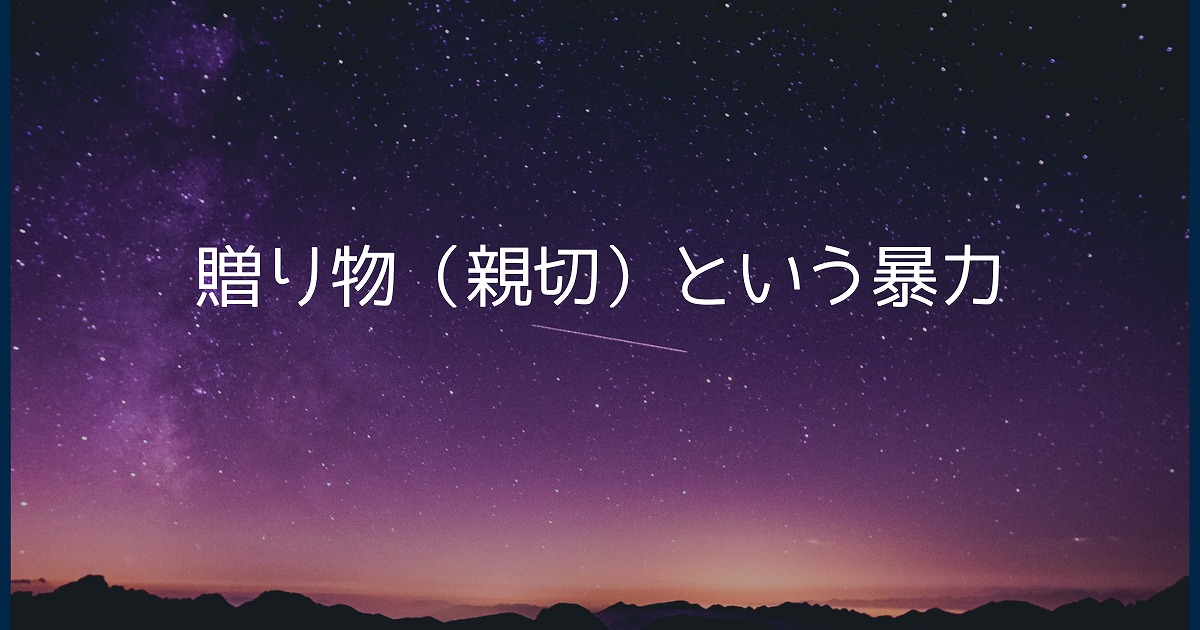


コメント